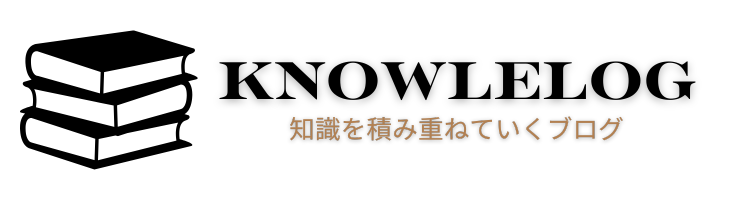さつまいもをホクホクに仕上げたかったのに、何故かシャキシャキとした食感に…。
そんな経験はありませんか?
実はこの現象には、さつまいも特有の性質や調理法が関係しています。
本記事では、「何故さつまいもがシャキシャキになるのか?」という疑問に答えながら、ふんわり柔らかく仕上げるための方法やポイントも丁寧に解説していきます。
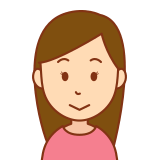
失敗知らずの美味しいさつまいも調理を目指したい方は、是非、最後までご覧ください。
さつまいもがシャキシャキする原因とは?
さつまいもを調理したときにシャキシャキとした食感になるのは、意外にも多くの人が経験している現象です。
その原因は主にデンプンの変化、品種の違い、保存方法や調理法によって引き起こされます。
ここでは、その理由をひとつずつ解説していきます。
デンプンの変化による影響
さつまいもには「βデンプン」と呼ばれる未加熱のデンプンが多く含まれています。
これが十分に加熱されて「αデンプン」に変化しないと、さつまいもの中心部分がシャキシャキとした食感のまま残ってしまいます。
特に加熱温度が低すぎる、または時間が短すぎると、デンプンの変化が不完全になりやすいのです。
品種による違いもある
さつまいもには「紅はるか」「シルクスイート」「安納芋」など、様々な品種があります。
実は、品種によってデンプンの構成や水分量に違いがあり、それが食感に影響します。
例えば、水分が少なくデンプン質が強い品種は、しっかり加熱しないとシャキシャキ感が残りやすい傾向があります。
保存状態や調理方法の影響
収穫直後のさつまいもはデンプンが多く含まれており、そのまま調理するとシャキシャキしやすいです。
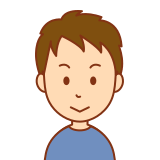
また、冷蔵庫など低温で保存するとデンプンの糖化が進まず、加熱してもホクホクになりにくくなります。
加熱方法もポイントで、急激な加熱では内部までしっかり火が通らず、芯が残ってしまうことがあります。
シャキシャキになりやすいさつまいもの特徴
さつまいもはすべてが同じようにホクホクになるわけではありません。
実際、シャキシャキしやすいさつまいもにはいくつかの特徴があります。
このパートでは、見た目や感触、選び方のコツ、収穫時期との関係などからその傾向を探っていきましょう。
見た目やカット時の感触
シャキシャキしやすいさつまいもは、切ったときに断面がやや白っぽく、水分が少なく感じられるものが多いです。
また、カットした際に「サクッ」とした固めの手応えがある場合、中心部分にデンプンが多く、加熱してもやわらかくなりにくい傾向があります。
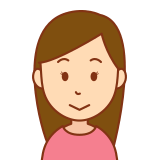
逆に、カットした断面が黄色っぽくしっとりしているものは、比較的ホクホクになりやすいです。
スーパーでの選び方のコツ
スーパーで購入する際は、皮がしっかりしていてヒビ割れがなく、持ったときにずっしりと重さを感じるものを選びましょう。
軽いものは水分が少なく、シャキシャキになりやすいことがあります。
また、袋詰めされた商品よりも、バラ売りのもののほうが状態を見極めやすく、質の良いものを選びやすいです。
収穫時期との関係性
さつまいもは収穫直後よりも、一定期間寝かせた「追熟」状態のものの方がデンプンが糖に変わり、柔らかく甘みが増します。
収穫後すぐに出回る時期(9月〜10月前半)は、まだ追熟が足りずシャキシャキしやすい傾向があります。
11月以降に出回る熟成されたさつまいもを選ぶと、ふんわり仕上がりやすくなります。
ふんわり柔らかく仕上げるための基本ポイント

さつまいもをふんわり、ホクホクに仕上げるためには、ただ加熱するだけでは不十分です。
温度や時間、水分量、加熱方法の選び方など、いくつかのポイントを押さえることで、食感が大きく変わります。
このパートでは、その基本的な調理テクニックを紹介します。
加熱の温度と時間の最適化
さつまいもは低温でじっくり加熱することで、デンプンが糖へと変化し、しっとりとした食感になります。
理想的な温度は70〜85℃前後。
この温度帯をキープしながら40〜60分程度加熱すると、ふんわり仕上がります。
オーブンや炊飯器の保温機能を活用するのもお勧めです。
蒸す・焼く・煮る、それぞれの工夫
加熱方法によっても食感は大きく変わります。
蒸す場合は蒸し器でゆっくり火を通すと、しっとり柔らかくなります。
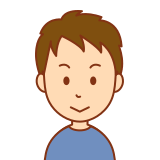
焼く場合はアルミホイルに包み、160〜170℃の低温で時間をかけて焼くのがポイント。
煮る場合は、水に酢や塩を少量加えると甘みが引き立ち、ホクホク感が出やすくなります。
水分量と加熱方法のバランス
加熱中に水分が抜けすぎるとパサつきやシャキシャキ感の原因になります。
蒸し器ではふたに付いた水滴が落ちないようにふきんを巻く、オーブン焼きではアルミホイルで包んで水分の蒸発を防ぐなど、工夫が必要です。
程よい水分を保つことで、ふんわり感が増します。
調理前にできる!シャキシャキを防ぐひと工夫
さつまいもを調理する前のちょっとした工夫でも、仕上がりの食感に大きな差が出ます。
このパートでは、下ごしらえや保存方法、追熟のポイントなど、シャキシャキ感を和らげるための事前準備を紹介します。
カット後の水さらしの大切さ
さつまいもを切ったあとに水にさらすことで、余分なデンプンやアクを取り除くことができます。
これにより、加熱中のムラが減り、全体的にやわらかく仕上がりやすくなります。
10〜15分程度、たっぷりの水にさらすのが目安です。
その後、しっかりと水気を切ってから調理しましょう。
冷蔵保存による影響と対策
さつまいもは寒さに弱く、冷蔵庫など低温で保存すると細胞が傷みやすくなります。
これが原因で加熱しても柔らかくならず、シャキシャキした食感が残ることがあります。
保存は常温(13〜16℃前後)で、新聞紙などに包んで風通しの良い場所に置くのがお勧めです。
追熟させることで食感を変える
収穫から1〜2週間ほど寝かせておくことで、デンプンが糖に変わり、よりしっとりと甘みのある仕上がりになります。
購入したばかりのさつまいもも、すぐに使わずに常温でしばらく置いてから使うことで、ホクホク感が高まります。
これは家庭でも手軽にできる方法なので、是非、試してみてください。
まとめ

さつまいもがシャキシャキしてしまう原因は、デンプンの性質や品種、保存・加熱方法など、様々な要因が関係しています。
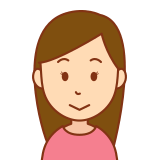
しかし、ポイントを押さえれば、ふんわり柔らかく仕上げることは十分可能です。
低温でじっくり加熱することや、調理前の水さらし、冷蔵保存を避けるといった工夫を取り入れるだけで、ホクホクとした理想的なさつまいもに仕上げることができます。
是非、この記事の内容を参考にして、毎回のさつまいも料理をより美味しく、楽しくしてみてくださいね。